06/9/16
すっかり忘れられている、というより、記憶さえしてもらっていないと思うけれども、まあ私自身が忘れていたこともあるが…、京都の町や学区について、語っていたのだった。
なぜ語っていたかというと、それが全国的に珍しいと思われたからだ。
「学区」という存在が、ヨソの地方に存在するのかしないのかを知らないので、果してそれが珍しいかどうかは良く分からないのだが、分からないまま書いていた。
居場所を特定するのに町名よりも通り名を使う、ことは多少ユニークかもしれない。
京都に住んでいると普通だと思ってしまっていて、あまりユニークだと思わないから、それがどれだけ独特かということに気がつかないことが多いのだ。
ただ、どの地域よりも各段にユニークで、独特だと思えることが、ひとつだけ確実にある。
それは、京都の町名の多さだ。
このことは、子供の頃はまったく気がつかなかった。
というより、別にそんなことは普段の生活に差し障りがあるわけではないから、どうでもいいことだ。
どうでもいいから、今までは気にも留めなかった。
確かにどうでもいいことだったのだが、気がついてしまった以上、とても気になる。私は覚醒してしまったのだ。そうなると、とことん追求しないではいられない性格なのだ。
そんなわけで、京都の町内についての話。
町、というよりも町内(ちょうない)と呼んだ方がしっくり来る。
「あの人、どこの町内の人?」等という会話が普通に行なわれている。町内という言葉は、既にひとつの言語として成立しているのだ。
京都の町内がどれだけ多いかは、郵便番号簿を調べれば分かる。
私の手もとにあるのは平成9年版(古い)の「ぽすたるガイド」というもので、もっと新しいものは、もうまったく違う構成になっているかもしれないが、とりあえず、この平成9年版で例にとってみる。
これは全国の郵便番号が載っている。郵便番号が七桁になった当初のもので、今では市町村の統廃合で、市町村名そのものが変わり、郵便番号も変わってしまっただろう。
京都市に関しては、京北町が北区に併合されたから、この時よりちょっぴり多くなった。
京都市のページは、この郵便番号簿では9ページある(裏、表を1ページとして)。
比較するために他の都市を見てみる。
東京都は何ページあるかというと、3ページしかない。
しかも、都内だけでなくて市も足してだ。東京は新しい都市なので、区画整理が進んでいるのかもしれない。
大阪は5ページだ。これは、府下も足してである。
京都は府下を足すと13ページになる。
他に多いのは愛知県で、10ページある。でも、名古屋市だけだと2ページしかない。
神戸と兵庫県もそんな感じだ。
京都と同じ古都の奈良はというと、全然多くない。奈良県全体で3ページ半しかない。
こうしてみると、いかに京都(京都市)が突出して町内の多い市かということが分かると思う。
(これは別に自慢でもなんでもなくて、ただ事実を述べているだけだ)
京都府全体で13ページ、そのうち9ページが京都市に費やされている。
京都市の面積は、よく分からないが、東京都の1/10くらいだとすると、さらにこのことがどれだけ異常なことかと気がづく。
東京よりも1/10も小さい地域に、東京の3倍もの町内がある。
そうすると、単純に考えれば、京都のひとつの町内は、東京の町の1/30の面積しかないことになる。
そんな町内があるのだろうか。
さらに、「ぽすたるガイド」には、冊子の最後に京都の地図が出ている。
「京都市の同一町域名」というタイトルで、下京区、中京区、東山区という、三つの区域の簡単な地図だ。
要するに、区域に同じ町名がいくつもあるから、それを図示してある地図である。
つまり、手紙を送る時に、同じ町名がいくつもあるとどの町に送るのかが分からず、ややこしいから、どこの町かをはっきりさせてもらうための措置なのだろう。
はじめ、私は、この最後についている地図は、京都に住んでいる人たちがもらうぽすたるガイドだけに付いている地図だと思っていた。
でも、京都へ手紙を送る人は全国にいるだろう。だから、これはやっぱり、どの地域のぽすたるガイドにも掲載されているのだろう(当たり前だ)。
これは、どういうことかと言うと、京都市ではあまりにも町内が多いので、時には同じ町名がついてしまう。
例えば、大黒町とか、材木町とか、塗師屋町、大工町、仏具屋町など。
同じ町名がいくつもあるのだ(時には、違う場所に三つ同じ町名があることも)。
それが例えば左京区と中京区に同じ町名があるのだったら、まだ区別がつく。
でもそれが下京区なら下京区に同一町名があったら、ややこしくてしょうがない。どのように区別したらいいのか。
そのために郵便番号を違わせてある。
京都の郵便屋さんは大変である。
京都市下京区大黒町という住所があったら、それは五条下ルなのか、仏光寺通なのか。
町名だけでは、京都市に住む我々京都人でさえ分からない。
だから、なるべくなら、京都の住所は通り名の、「室町五条下ル」とか、「仏光寺麩屋町東入ル」などと書く方が分かりやすい。
だからこそ、通り名表記が発達した。
一般の京都人は、だから、普通は町名を使わない。通り名のみで生活をしている。
だから京都人は、京都の町名を知らないことが多い。あまりにも多いから、覚える気さえないのだ。
いったい、京都の町内はどうなっているのか。
もう少しぽすたるガイドを見てみたら、面白いことが分かった。
東京の、例えば荒川区という項目を見ると、町がわずかに七つ。
では、京都の例えば、ええと、町内の数が少なそうな東山区にはいくつ町があるかというと、ええと、これが数え切れない。多分、100以上あるだろう。
それくらいの数である。
京都はひとつの区に、そのくらいの数の町内があるのだ。
(これは、新興地の左京区や右京区でも同様。百以上ある)
では、下図の地図を見てみよう。これは、私の町内のモデルだ。
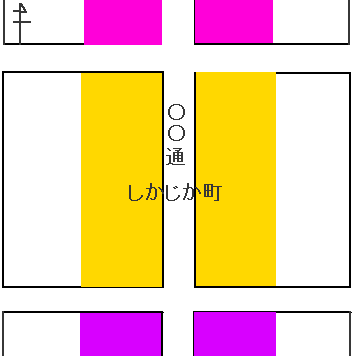
これは、南北の通りを基準にして、町が成り立っている場合で、もちろん東西の通りをまたいでの所もあるだろう。
この図でいうと、○○通を挟んで向い合わせになっている家々が、ひとつの町内を形成している。
正確にいうと、ワンブロックの北側の東西の通り半分から南側の東西の通り半分も含むので、南北の通りを挟んで、コの字形に通りに面した部分がひとつの町内になる。
黄色く塗られている部分がひとつの町内で、ピンクとか紫は、また別の町内になる。
この場合、南北の○○通りを挟んだ向かいの家と家は同じ町内だ。
しかし私の家は東西に面した通りにあるので、向かいの家は、別の町内だ。
そして、隣の隣の家が別の町内との境目なので、2軒向こうの家は私の家とは別の町内になる。
京都の家と町内はたいていこんな感じなので、向かい合っている家が別の町内である、ということは当たり前だった。
通りをひとつ歩けば、そこは別の町内なのだ。だから、まったく別の生活区域がそこにある。
メートルに換算すれば(大雑把だけど)、200メートル四方がひとつの町内、という感じだ。
向かいの家なのに別の町内、というのは家は近くてもものすごい距離感があり、お向かいさん、ではなく、向こうの町内の人、というくらいの隔絶した存在になる。
その代わり、自分の町内の人々とは、ものすごい緊密な連携をとるのである。
私の家のある町内は全部で40軒ほどだと思う。おそらくどの町内もそれくらいの家の数だろう。
それがさらにいくつかの班に分かれていて、連絡を取り合い、町会長さんと結び付いている。
町会長と言っても、40軒ほどの中から選ばれるわけだから、そのうち順番で回って来る。
落語に出て来る長屋を、ほんのちょっとだけ規模を大きくした感じだ。
こういう町内のありかたは、他の都市とどう違うのか、同じなのか、私がヨソに住んだことがないから良く分からない。
ただ、京都の町内が全国的に見ても異常に数が多い、ということだけが、分かっている事実だ。
最近では、中心部にマンションが増えている。そういう区域には、町内の人員の数が百人以上、という所もある。マンションに暮らす人がいっきに町内人員に含まれるからだ。
京都でひとつの町内に百人以上いる、というと、へー、えらい人が多いなあとびっくりされる。
京都市に全部でいくつの町内があるのか、それはもはやほとんど天文学的な数字であり、正確には知らない。
初めに言ったように、同じ町名もたくさんある。
塗師屋町とか仏具屋町など、いかにもな名前が数多い。
その昔、町名を決める時、ここには仏具屋さんが多いから仏具屋町にしよう、という感じで安易に決めていったのだろう。
ところが、京都にはお寺が沢山あり、お寺の門前には必ず仏具屋さんが建つから、仏具屋町という同じ町名があちこちに出来てしまった。
こんな風にして、同じ町名がわんさと表れてしまった。
それが別段不自由でもなかったのは、再三言っているように、京都では碁盤状態に通りが走っていて、それによる通り名表記が発達したからだ。
いつごろから通り名表記が発達したのかというと、私は室町時代ではないかと睨んでいる。
大した根拠はなく、まあ、京都におけるこのような類いの文化的痕跡は、室町時代からであることが多いからだ。
町名も同じく、みやこに商人が集まり、都市を形成し始めた室町時代に由来するのではないだろうか。
そんなわけで、室町時代における町割りが今も生きているために、京都では、せせこましい町内生活を今でも営んでいるというわけである。